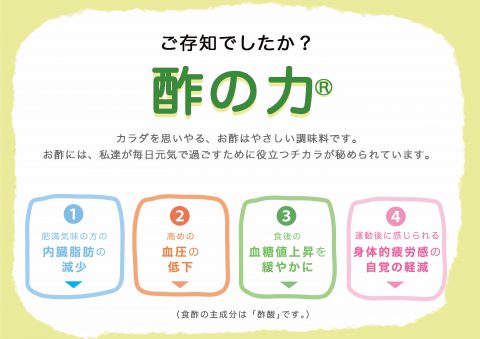はじめに
みなさん、こんにちは。
お酢博士の赤野です。
お酢の歴史や雑学など、お酢をたのしくおもしろくお伝えしてまいります。連載第1回目となる今回は、みなさんに身近な「地名」のお話からはじめましょう。
お酢ご一行さまが通った「御酢街道」
全国には食に関わる地名や名前が数多くありますが、お酢に関わる地名ももちろんあります。そのひとつが「御酢街道(おすかいどう)」。
御酢街道とは、神奈川県の平塚市から東京へ続く「中原街道」の別名です。東海道の脇街道として、旅人や商人の往来、農産物の運搬など、さまざまな人とものが行き来してきました。
この平塚の中原地区というところでは「成瀬酢」というお酢が作られていて、江戸までの最短ルートである中原街道を通って江戸城に献上されていました。お酢を献上する際に通った道ということで「御酢街道」と呼ばれているそうです。
家康はお酢が好き?
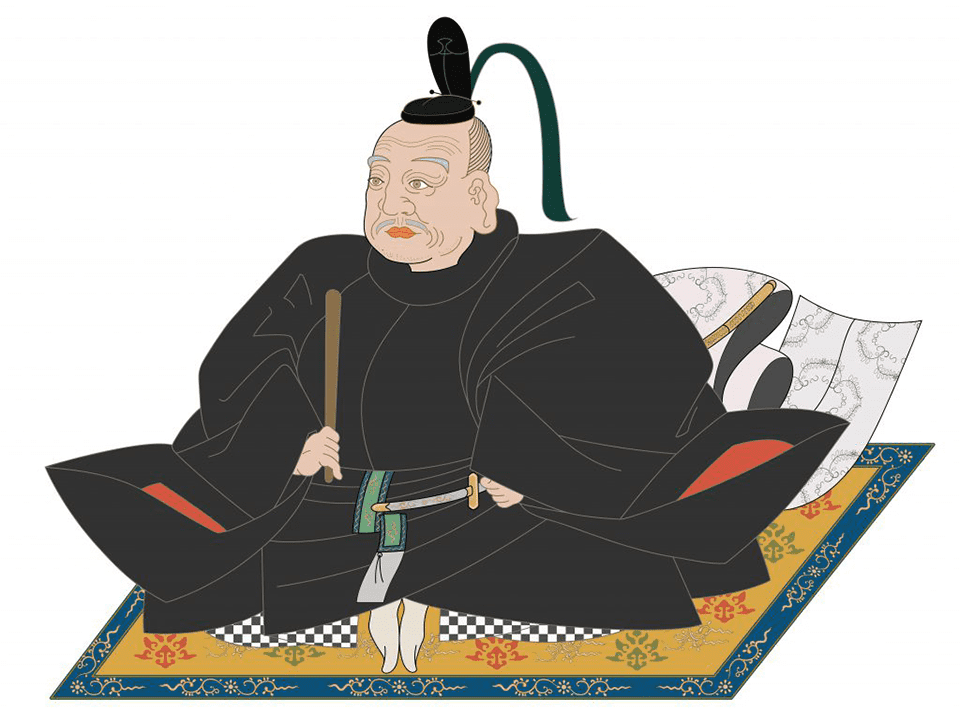
さて、この平塚の成瀬酢についてもう少し詳しくお話しましょう。
平塚の平塚宿から約2キロ離れたところに、家康は鷹狩の拠点とした「中原御殿」という別荘がありました。この中原御殿の正面にはお酢を扱う酢屋があり、中原御殿に滞在中の家康にお酢を献上したところ、とても気に入って定期的な献上品になったといわれています。
家康は健康への意識が高く、食事や食材にも気を使っていた人物。家康もお酢が好きな“酢好きさん”だったのかもしれませんね。
家康のお酢の食べ方は、お酢を皿にとって鯛などをつけて食べるスタイルだと私は推測しています。家康は保守的なタイプなので、新しい食べ方よりも昔から続くシンプルな食べ方を取り入れていたのではと考えています。
お酢街道を通った人たち
家康への献上品を運ぶお酢ご一行さまは、藤沢、川崎を通過したのち、多摩川を超え、江戸城に向かいます。定期的にお酢をおさめていたので、お酢の道として広く知られるようになったのではないでしょうか。
御酢街道は、東海道よりも短いルートであるため、庶民や物資のほかさまざまな人が通りました。討入前の赤穂浪士もお酢街道を抜けて江戸に入ったと言われているんですよ。
「酢」のつく地名にはやはりお酢にまつわる歴史がありました。
ほかにも日本にはお酢の地名があるようです。ぜひお酢博士の記事をご期待ください。
撮影/楠 聖子(赤野さん)
取材・文/おいしい健康 編集部
関連記事
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます